20XX年〇月△日(休職から307日目)
リワークデイケアではSSTという授業がある。
[Social Skills Training]の略語で、円滑な社会生活・人間関係を構築するためのスキルを、
トレーニングするための授業。
今は傾聴というスキルを学んでいる。
一生懸命相手の話を聞くこと。
でも、この傾聴って言うのが奥が深い。
傾聴っていうのは、相手に【関心を持つ】ってことです。
教えてくれた職員が言っていた。
ただ話を聞けばいいってわけじゃない。
話を聞いてくれているなって相手に伝わればいいってわけじゃないんだ。
そのなかで特に感銘を受けたのが『非言語の傾聴』って考え方だ。
言葉が無いのに傾聴するってどういうこと?
話を聞くんだから、言葉が無いと傾聴って言わないんじゃないの?
でも、【関心を持つ】って前提があれば、『非言語の傾聴』もたしかにある。
奥が深いと思う。
そもそも傾聴スキルとは?

傾聴スキルは「相手の話を一所懸命聞くこと」。
もしくは相手に話を聞いていると感じて貰うこと。
傾聴って奥が深いと思うから、色んな答えがあると思う。
でも、傾聴の意味合いの1つに、たしかに上記があると思う。
「ちゃんと話を聞いてくれているな」
「ちゃんと理解しようとしてくれているな」
そう感じると、相手は嬉しくなり安心感を得られる。
そうすると、どんどん話が進み、会話が弾み、好感が持てるようになる。
まさにSST[Social Skills Training]の要と言えるだろう。
具体的には下記のようなスキルがある。
- あいづち
- うなずき
- 繰り返し言う
- 質問する
- 感想言う
逆にこれらの反応ない相手に話をしても、
どんどん悲しく嫌な気持ちになり話したくなくなっていく。
この反応だけで話し手は「無関心」と捉えてしまうのだろう。
そういう面でも面白く奥が深いと思う。
非言語の傾聴とは?
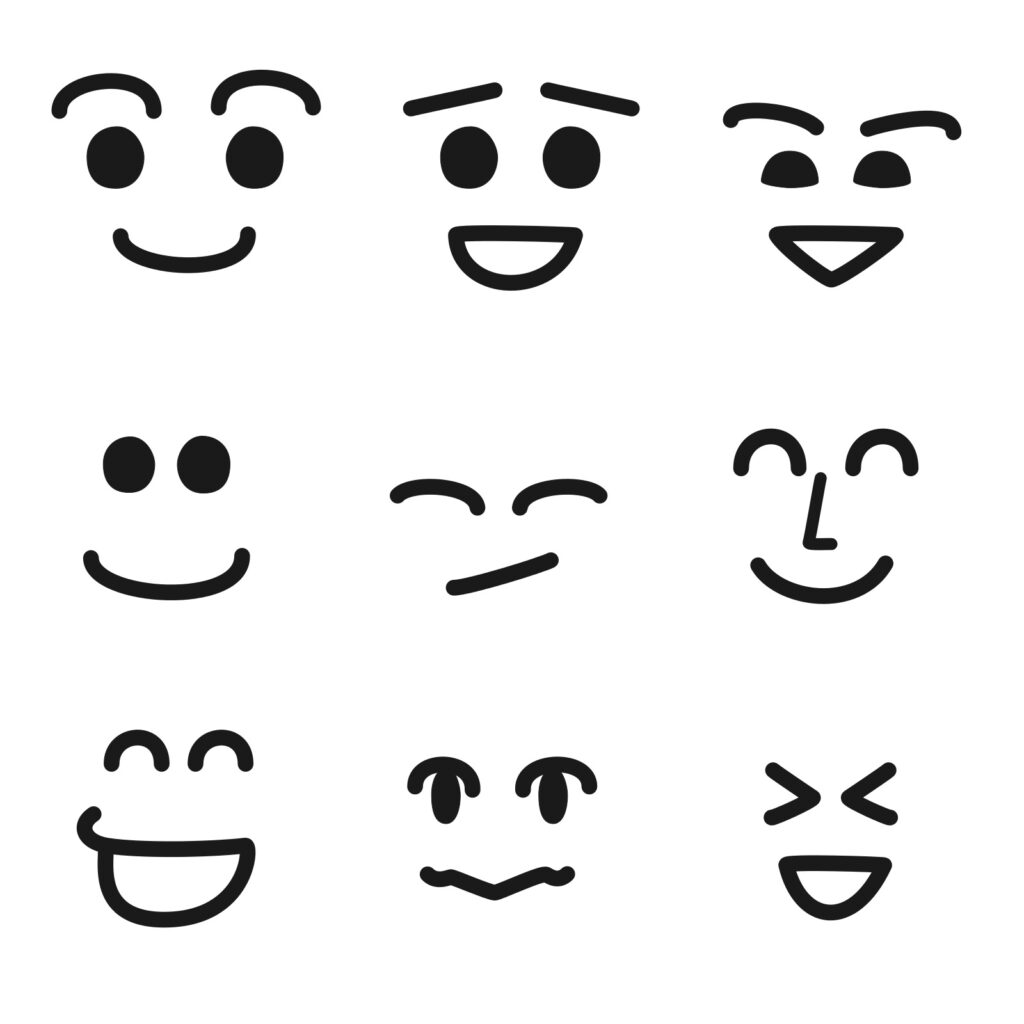
つまり、やはり「関心を持ってくれているか否か」が重要になってくる。
そして別の機会に相手がその話を振ってくれたら「覚えててくれていたんだ」って嬉しくなる。
普段から関心を持って観察することがいいんじゃないか。
そんな意見があった。
話している時以外にも、仕草や表情、反応など一挙手一投足を見ていると、
相手の人となりが分かってきて、関心が出てくるというのだ。
非言語の傾聴と言えるでしょうね。
仕草や表情、動作を観察することで関心を持ち始め、
いざコミュニケーションを図る時にお互いが好感を持ちやすくなる。
その事前準備かな?
普段から観察することも大切なのかもしれないね。
単に話を聞くことだけが傾聴ではない。
相手に関心を持つこと。
そのために普段から観察すること。
それも傾聴といえるのではないだろうか?
非言語の傾聴って考え方は僕にはなかった。
今後意識してみよう。
良いことを学べた気がする。
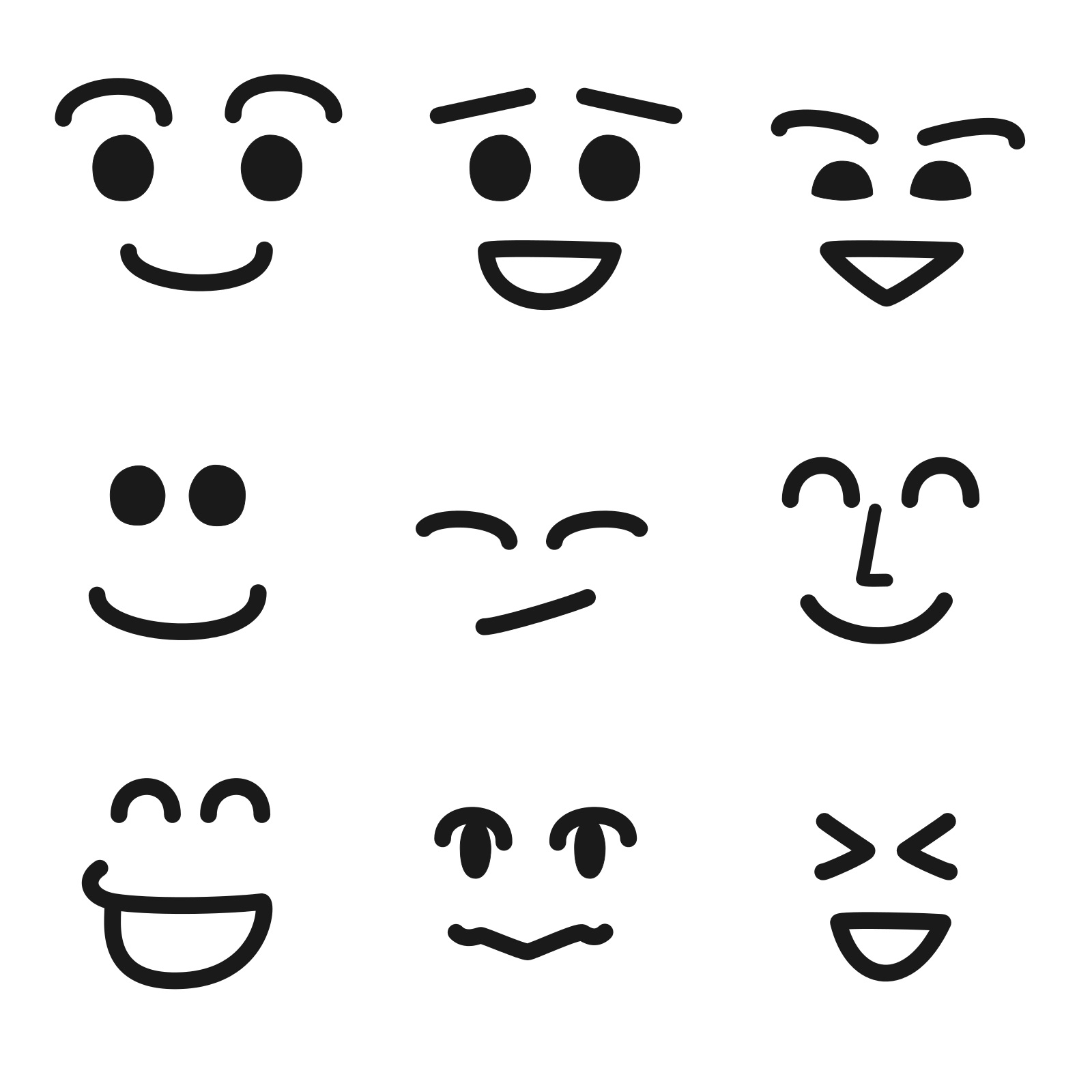


コメント